はじめに
みなさんこんにちは!ゆいパパです。
この記事は、1歳1ヶ月の娘が川崎病と診断されたときの実体験を記録したものです。
突然の発熱、診断、入院、そして退院後の不安な日々ーー。
私自身、この経験を通じて「親としてどんな行動ができるか」をたくさん考えました。
今、お子さんが川崎病と診断されたばかりで不安を抱えているご家族がいたら、ほんの少しでも気持ちの支えになればと思い、この記事を書くことにしました。
川崎病ってどんな病気?
川崎病は、主に4歳以下の乳幼児に多くみられる血管の炎症性疾患です。
原因ははっきりとはわかっていないみたいですが、以下のような症状がいくつか重なることで診断されます。
- 5日以上続く高熱
- 両目の充血
- 口唇の赤み、イチゴ舌
- 手足のむくみ、皮むけ
- 発疹
- 首のリンパ節の腫れ
重症化すると心臓の冠動脈に瘤(こぶ)ができるリスクがあり、早期治療がとても重要と担当医の方から説明を受けました。
発症の経緯〜診断まで
娘が川崎病と診断されたのは、1歳1ヶ月のとき。
最初は発熱だけで、近所の小児科を受診した際は「突発性発疹の可能性もありますね」と言われ、特に大きな病気だとは思っていませんでした。
でも、熱は下がる気配がなく、7日間ずっと高熱が続きました。
「なんかおかしいよね」と夫婦で感じていた頃、再度小児科を受診したところ、目の充血を見た医師から「今すぐ大きな病院に行ってください」と言われました。
妻からその連絡を受けた瞬間、背筋がゾッとしたのを覚えています。
その後すぐに労災病院で検査を受け、目の充血やハンコ注射痕の赤みなどから**「典型的な川崎病の症状です」**と診断されました。
その時点で、私は川崎病という病名すらよく知りませんでした。
慌ててネットで調べ、「後遺症」「冠動脈瘤」「入院」などの文字に強い不安を感じたのを覚えています。
入院生活

入院期間は7日間。治療はアスピリンの投与で、点滴がずっとついていました。
採血や心エコーの検査でぐったりした娘は、最初の数日はずっと寝ている状態で、食欲もあまりありませんでした。
病室は4〜5人部屋で、20時で面会終了となると、親たちは帰宅しなければなりません。
そのときの子どもたちのギャン泣きする声が胸に刺さりました。娘も雰囲気を察したのか大泣きしていて、置いて帰るのがとてもつらかったです。
基本的には妻が日中ずっと付き添ってくれて、私は仕事を調整して毎晩面会に行き、食事の時間に間に合うようにしていました。
おもちゃの持ち込みができたので、家でいつも遊んでいたおもちゃを持っていけたのは正解でした。
病院側が用意していた体に巻くタイプのアイシングも便利だったので、後日自分でも購入しました。
夜勤の看護師さんがいつも同じ方で、娘の様子を丁寧に見てくれていたのも大きな安心材料でした。
また、隣に入院していた男の子が「ゆいちゃん、お昼ご飯いっぱい食べてたよ」と声をかけてくれて、気持ちがふっと和らいだのも印象に残っています。
退院後の経過と注意点
退院後の娘は少し体力が落ちていたようで、歩こうとしても尻餅をつくことがありました。
でも食欲は回復していて、「いつものゆいが戻ってきた!」と夫婦でほっとしたのを覚えています。
ただ、退院から1週間後にまた39度近い熱が出て、急いで緊急外来へ。
結果的に川崎病とは関係のない発熱とわかり、胸をなでおろしました。
今はアスピリンの服用を続けており、2ヶ月間の内服が必要とのこと。
服用中に感染症(インフルやコロナ)にかかると稀に後遺症のリスクがあると聞いて、外出は今も控えめにしています。
感染症対策は家族全員で意識しており、自分も職場でマスク・手洗いを徹底しています。
川崎病を経験して思うこと
この経験を通じて思ったのは、親の直感ってすごく大事だということです。
「なんかいつもと違うな」「元気ないな」「ずっと抱っこを求めてくるな」
そんな小さなサインを見逃さず、医師に正直に伝えることが、診断と治療の早さに繋がったと思います。
あの頃の自分に声をかけるとしたら、
「今はもう元気に公園を歩き回ってるよ。大丈夫、ちゃんと乗り越えられるよ」って言ってあげたい。
そして、面会を頑張ってくれた妻に感謝の気持ちを込めてごはんをごちそうしたのは、よかったと思っています(笑)。
同じように不安な時間を過ごしているご家族へ
今、お子さんが川崎病と診断されて不安でいっぱいの方もいるかもしれません。
うちの娘は1週間で退院できましたが、入院が長引くケースもあります。
正直、「絶対大丈夫」とは言えません。
でも、子どもがピンチのときほど、親が冷静になることが大切だと感じました。
「何が不安なのか」「どんな情報がほしいのか」
そうやって自分の気持ちを言葉にしてみると、医師にも相談しやすくなり、不安が少しずつ軽くなっていきます。
この体験記が、どこかの誰かの安心材料になりますように。
おわりに
川崎病は、いつどんな家庭でも起こり得る病気です。
でも、親の観察力・病院との連携・周囲の支えがあれば、きっと乗り越えられると僕は思っています。
読んでくださってありがとうございました。
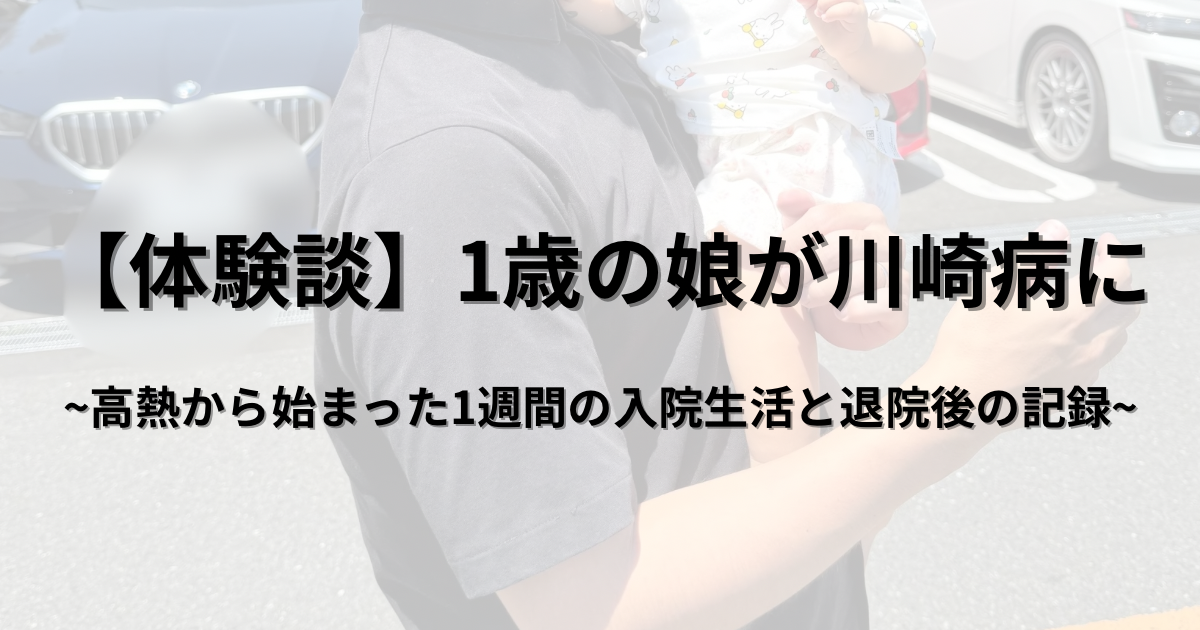

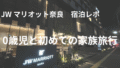
コメント